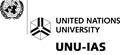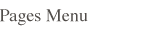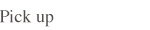2025年3月18日から19日まで、国連大学OUIKは国内外から参加した専門家や関係者と共に能登半島の被災地を訪問し、地域の被害状況、そして伝統文化・自然資源・地域のつながりを活かした復興の現場を視察しました。
視察メンバーは、ユセフ・ナセフ(UNFCCC適応部門ディレクター)、シャオメン・シェン(国連大学欧州事務所(UNU-VIE)副学長、国連大学環境・人間の安全保障研究所(UNU-EHS)所長)、⼭⼝しのぶ(UNU-IAS 所⻑)、武内和彦(IGES理事長)、トーマス・エルムクビスト(ストックホルム大学ストックホルムレジリエンスセンター 教授)、齊藤修(公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)上席研究員/東京大学未来ビジョン研究センター客員教授)、小島三津雄(UNU-IAS評議員)、渡辺綱男(UNU-IAS OUIK客員研究員)、小山明子(UNU-IAS OUIK研究員)、フアン・パストール・イーバルス(UNU-IAS OUIK研究員)、富田揚子(UNU-IAS OUIKプログラム・コーディネーター)の11名でした。
初日の午前、輪島市在住の萩野夫妻(まるやま組)を訪問しました。夫妻は地域に根ざした伝統的知識や建築文化の価値を伝えてくださいました。地震によって地域の伝統的な住居が甚大な被害を受け、電気・水・食料などのライフラインも一時的に失われた中での保存食や地域の水源を使った自給自足的な暮らしと、防災についてもお話しいただきました。「急がず、景観やコミュニティの特性を尊重しながら着実でレジリエントな復興を進めたい」との考えを強調されました。

萩野さんによるまるやま組の活動についてのプレゼンテーション
午後、視察団は地震そしてその後の豪雨災害で大きなダメージを受けた輪島市町野地区を視察した後、輪島キリモトで桐本順子さん(輪島キリモト副代表)から伝統的な漆器産業の復興についてお話を伺いました。桐本さんは災害で傷ついてしまった漆器を生かして新しい作品を作る「輪島塗RESCUE&REBORNプロジェクト(生まれ変わらせる漆器)」という新たなプロジェクトについてご紹介いただきました。

輪島キリモトの副代表、桐本順子さん
翌日は珠洲市で昔ながらの手仕事で炭焼きを行っている大野長一郎さん(株式会社ノトハハソ代表)を訪れ、震災後の炭づくり、そして今後の森づくり、地域づくりの取り組みについてお話しを聞きました。さらに地震に強い窯の開発や移転先の新しい工場のオフグリッド化、そして地域の防災に関する計画など、地域全体のレジリエンスを炭焼き通してどう高めて行けるか、様々なアイデアを共有いただきました。
その後、視察団は金沢大学能登学舎を訪れ、中村華子さん・山下修平さん(金沢大学能登学舎スタッフ)から能登里山里海SDGsマイスタープログラムについて説明を受けました。このプログラムは10年以上にわたり地域のリーダーを育成し、震災後も地域活性化に寄与しています。宇都宮大輔さん(珠洲市自然共生研究員/能登SDGsラボコーディネーター)から能登SDGsラボの持続可能な地域づくりに向けたこれまでの取り組みを紹介いただきました。
次に珠洲市の若山地区を視察し、河川の浸食や住宅の被害、崩れた斜面など深刻な被害状況を直接観察しました。気候変動に伴うリスクの軽減策として、Eco-DRR(生態系を活用した防災・減災 )の導入が急務であると認識されました。
最後に珠洲市役所で泉谷満寿裕市長と会談し、震災、豪雨災害の影響、現状、そして今後の復興について議論しました。市長は地域住民が災害のリスクがある土地にもかかわらず故郷に戻りたいという強い思いを持っていることを述べ、その思いを尊重したレジリエントな復興が今後の課題であると語りました。

珠洲市役所にて泉谷満寿裕市長との会談
この2日間の能登半島視察を通じて、参加者は、災害の爪痕が残る地域の現状や課題に触れると同時に、伝統的知識や自然との共生の中に、地域の未来を切り拓く力があることを実感しました。被災地の景観やコミュニティを尊重した復興、文化産業の再生、人材育成、自然を活かした防災は、持続可能な地域づくりへの重要な示唆です。
UNU-IAS OUIKは、こうした学びを今後の研究や発信に活かすとともに、これからも地域の皆さんと共に歩み、持続可能でレジリエントな復興を目指して取り組んでいきます。