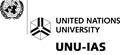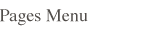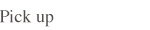2025年6月27日、能登島小学校5年生の皆さんと、能登島長崎町の岩礁海岸にて里海の生きもの調査を行いました。国連大学も活動を支援している能登GIAHS生物多様性ワーキンググループと七尾市で企画・準備を進め、ワーキンググループの荒川裕亮さん(のと海洋ふれあいセンター)が講師を勤めましました。現地では他のワーキンググループのメンバー、伊藤浩二さん(岐阜大学)、小山明子研究員(国連大学)や、地元の源内伸秀さん(能登島自然の里ながさき)に加え、今回は木森喜大さん(のとじま水族館)も活動をサポートしました。
はじめに、七尾市の小竹さんのお話を聞きながら、今日のスケジュールを確認しました。続いて、講師の荒川さんから里海の生き物の生息している環境について、ワーキンググループが作成した下敷き教材を用いて説明頂きました。その後、活動時の注意点を聞いてから、一同はライフジャケットとマリンブーツを着用し、箱メガネと採集した生き物を入れるバケツを持って海岸に移動しました。護岸の上から海をのぞき込むと、小さな魚たちが泳いでいるのが見え、期待が高まります。岩場の浅瀬にて、いよいよ生き物採集の時間です。
震災の影響で七尾湾は少し沈降しており、例年よりも水位が高くなっているとのことでしたが、子どもたちはそんなことは気にも留めず、元気いっぱいに海へと入っていきます。一見すると生き物の姿はあまり見えませんが、目をこらして観察してみると、小さな貝がたくさん見つかります。岩の上にびっしりと集まったアラレタマキビを見つけ、「いっぱいおる!」と嬉しそうにバケツに入れる児童もいました。素早く動く魚を捕まえようとしたり、岩のすき間にいるカメノテを一生懸命引っ張り出そうとしたりと、それぞれが工夫を凝らしながら、生き物探しに夢中です。足を滑らせそうになった友達にさっと手を差し伸べる姿もあり、自然の中で助け合う様子も印象的でした。活動の後半になると、腰のあたりまで水に浸かりながら、両手で箱眼鏡を構えて海の中をのぞき込む児童の姿も。まるで泳ぐようにジャブジャブと移動しながら、生き物を探し続けていました。短い時間でしたが、それぞれに生き物との出会いを楽しんでいる様子でした。
続いては、グループごとに捕まえた生き物を判別する時間です。講師の先生の説明を聞きながら、ワーキンググループのメンバーが作成した里海の生き物の下敷きと照らし合わせて、生物の名前を確認し、種名を記録していきます。スガイとほかの貝のふたの形の違いを教わったり、「このカニは何だろう?」と種類を見比べてみたりと、興味深そうに生き物への理解を深めていく様子が見られました。小さなカキを見つけたグループでは、「食べたい!」と声を上げる子もいて、海の恵みに対する素直な反応が印象的でした。実際に手に取ってじっくり観察し、生き物とのふれあいを満喫していました。
観察会を行った能登島長崎町も、能登半島地震によって大きな被害を受けた地域のひとつです。その場所で、再び地元の子どもたちと一緒に自然に触れ合う機会を持てたことは、とても意義深いものでした。この生き物調査をきっかけに、自分たちの暮らす地域の自然や生き物にいっそう関心を持ち、今後もさまざまな活動を通じて理解を深めていってくれることを期待しています。