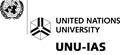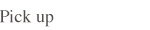金沢の日本庭園の活用方法を防災、観光、景観など多面的なアプローチから解説すると共に、持続可能な都市と生態系保全に向けたアイデアを提唱しています。
金沢:アーカイブ
OUIK 生物文化多様性シリーズ#5 金沢の庭園がつなぐ人と自然 ー持続可能なコモンズへの挑戦ー
国連持続可能な開発目標に向けた 青年キャパシティ・ビルデン グ・ワークショップ
日時 / Date : 2016/07/15 13:00 -17:00
場所 / Place : 金沢大学中央図書館 オープンスタディオ 2階
国連大学サステイナビリティ高等研究所と金沢大学留学生センターは、日本で学ぶ留学生によるSDGsワークショップを開催します。このワークショップは、7月11日から14日まで行われる、金沢市を中心としたSDGs達成のためのフィールドワークの報告会を兼ねています。金沢大学留学生センターに在籍する留学生、国連大学サステイナビリティ高等研究所のアカデミックプログラムの修士、博士課程で学ぶ留学生が「創造都市・金沢」を建築、エネルギー、教育、自然資源管理などの側面から議論します。
SDGsに興味がある皆様のご参加をおまちしております。言語は英語のみとなります。 ご登録は ryukou@adm.kanazawa-u.ac.jp まで氏名、御所属を記載のうえお送りください。
OUIK 生物文化多様性シリーズ#4 「地図から学ぶ北陸の里山里海のみかた」
OUIK初のマップブックとして、北陸地方の里山里海の現状や変化、多様な見方を地図から学ぶ教材を発刊しました。北陸地方(石川、福井、富山、新潟、岐阜)のスケール、石川県のスケール、七尾湾のスケールといったマルチスケールでの地図情報をまとめています。(PDF:95MB)
関連ページ(Collections at UNU) http://collections.unu.edu/view/UNU:6540
【開催報告】都市生態系再生国際シンポジウムin 金沢 「金沢から考える 都市の緑と文化、人々のつながり」 を開催
2025年5月22日、金沢市文化ホールにて、都市生態系再生国際シンポジウム「金沢から考える 都市の緑と文化、人々のつながり』が開催されました。世界中で都市が進化を続けるなかで、自然、文化、そしてコミュニティのつながりは、都市のアイデンティティをかたちづくり、持続可能な未来への道を拓く重要な要素です。本シンポジウムは地域住民の参画や文化的資源を生かした都市生態系の再生について、国内外の専門家やモデル都市・パイロット都市の代表者が意見を交わしました。
シンポジウムは村山卓(金沢市長)による開会あいさつで始まりました。その後、基調講演では以下3名にご登壇いただきました。
- ユリア・ルブレバ(国際連合環境計画(UNEP)都市自然、アソシエイトプログラムオフィサー)
- イングリッド・コッツィー(イクレイ アフリカ事務局 自治体生物多様性・自然・健康担当ディレクター)
- 鈴木渉(自然環境局自然環境計画課生物多様性戦略推進室 室長)。
ユリア・ルブレバ(国際連合環境計画(UNEP)都市自然、アソシエイトプログラムオフィサー)は「人と地球のための都市自然:生態系の再生とコミュニティの再構築」をテーマに発表し、健康でレジリエントな都市を築く上で、自然の果たす役割の重要性が認識されてきていると強調しました。単に美しさのためではなく、この変化する世界において、生命を維持し、文化を育み、コミュニティを強化する能力を持つためには、都市と自然を再びつなぐことが重要であると述べました。
続いて、イングリッド・コッツィー(イクレイ アフリカ事務局 自治体生物多様性・自然・健康担当ディレクター)は「都市のウェルビーイングとレジリエンス、そして人と人をつなぐ自然の力」をテーマに発表し、生態系と人間のウェルビーイングの強いつながりを反映した都市の例を紹介しました。さらに、パートナーシップと積極的なコミュニティ参加の重要性を述べました。
鈴木渉(自然環境局自然環境計画課生物多様性戦略推進室 室長)は、「自然共生社会の実現に向けた都市の役割」をテーマに発表し、生物多様性の改善のためには、緑の保全・再生、気候変動対策、持続可能な生産、消費の抑制を同時に進める必要があると強調しました。また、2020年以降の生物多様性世界枠組み(GBF)の実施、日本の新しい生物多様性国家戦略や地域レベルでの自然ベースの具体的な活用まで、世界、国、地域をつなぐ貴重な洞察を述べました。
後半のパネルディスカッションでは 内田東吾(イクレイ日本事務局長)がモデレーターを務めました。パネリストには、以下8名が参加しました。
- ジェイラン・サフェット・カラウラン・ソズエル(トルコ・イスタンブール 戦略開発プログラムコーディネーター/都市デザイナー)
- アンソニー・ポール・ディアス(米国・シアトル 公園・レクリエーション部長)
- フランソワ・モロー(フランス・パリ 都市生態学庁長)
- キンバリー・アンネ・ステーセム(カナダ・トロント 都市林業部長)
- ラウラ・エルナンデス・ロサス(メキシコ・メキシコシティー生物多様性戦略コーディネーター)
- ジュディス・アニャンゴ・オルオーチ(ケニア・キスムCECM(郡執行委員会委員-大臣)水、環境、気候変動、自然資源担当)
- フアン・パストール・イーヴァルス(日本・UNU-IAS OUIK研究員)
- 池田徹大(日本・金沢市文化スポーツ局文化財保護課)
「文化と自然から考えるコミュニティ主導の都市再生:世界の視点から」というテーマで、パネリストが各都市活動を紹介、経験を基に意見を交わしました。
- イスタンブール(トルコ)では、都市空間における自然の回復を目指す「アーバン・リワイルディング(都市再野生化)」プロジェクトが進行中であり、生態系の再生と市民の自然との共生を図っています。
- シアトル(米国)では、地域住民のボランティアが中心となり、都市内の自然再生活動に積極的に取り組んでいます。これにより、市民参加型のエコシステム保全モデルが構築されています。
- パリ(フランス)では、市庁舎前の広場の緑化が進められており、都市の中心部における自然環境の創出が実現されつつあります。
- トロント(カナダ)では、先住民族との和解を基盤とした生物多様性回復への取り組みが展開されており、伝統的知識と都市政策の融合が進んでいます。
- メキシコシティ(メキシコ)では、都市自然の保護・発展を目的としたネットワークの形成や、女性のリーダーシップ、地域コミュニティの参加を促す活動が行われています。
- キスム(ケニア)では、住民主導の取り組みによって、ヴィクトリア湖の環境回復が進められています。地域に根ざした保全活動が実を結びつつあります。
- 金沢(日本)では、用水や庭園システムを活用した都市内生態系の保全に加え、地域の伝統的知識と住民の協働による自然との共生が推進されています。
パネルディスカッションでは、シンポジウムの前に行われた視察やワークショップに参加したパネリストたちが、金沢で学んだことや経験したこと、それぞれの都市に持ち帰りたい見識や印象を共有しました。特に金沢市の用水活用、庭園や地域主導のホタルの保護活動について、印象的であったと述べました。さらに、パネリストは、猛暑、洪水、有害農薬、湖汚染、資金確保の難しさなど、各都市が直面している課題についても言及し、持続可能な都市を構築するためには、グリーン、ブルーインフラを増やすだけでなく、自然に基づく解決策 (Nature-based solutions) を採用することが重要であると強調しました。各都市で課題は異なるが、課題解決にはコミュニティの参加が重要であると締めくくり、ディスカッションを終了しました。
最後に、閉会時の挨拶で山口しのぶ(国連大学サステイナビリティ高等研究所 所長)は、パネルディスカッションで共有された各都市の事例を引き合いに出しながら都市生態系の再生は「人の関わり」によって実現するものであり、自然は人が関与することで豊かになると強調しました。さらに「生態系の回復とは、同時に関係性の回復でもある」と述べ、人と場所、過去と未来、そして同じ都市空間を共有する多様なコミュニティのつながりを再構築することの重要性を語りました。
本シンポジウムは、UNU-IAS OUIK、環境省、金沢市の共催のもと開催されました。また、国連環境計画(UNEP)、持続可能な都市と地域をめざす自治体協議会(イクレイ)日本事務局、石川県、北國新聞社にご後援いただきました。
詳細については以下の動画(シンポジウムの録画)をご視聴ください。
※関連記事:・都市にて自然と文化のつながりを深める解決策を紹介 – Institute for the Advanced Study of Sustainability
菊川地域でホタル調査を実施― 都市に残る自然の豊かさを再確認
2025年6月27日、国連大学サステイナビリティ高等研究所 いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(UNU-IAS OUIK)は、金沢市の菊川地域にて市民参加型のホタル生息調査を実施しました。本活動は、OUIKのSUNプロジェクト(持続可能な都市自然プロジェクト)の一環で、菊川公民館との共催により行われたものです。
調査に先立ち、金沢ホタルの会会長であり、石川ホタルの会事務局長でもある新村光秀さんによる講義が行われました。新村さんは、長年にわたり金沢でホタル保全に携わってこられた経験から、ホタルの生態や生息環境の条件、そして地域と協働した保全活動の意義について丁寧に解説しました。「ホタルは都市自然の豊かさの象徴。地域に残る用水や庭園が、ホタルの生息を支えている」と語られました。
続いて、OUIKのフアン研究員からは、都市における「生物多様性」や「生物文化多様性」の意義についての説明がありました。ファン研究員は、金沢の用水や庭園のような身近な自然環境が、文化的な営みと深く結びついてきた背景を紹介し、そうした都市自然を守り育てることが、地域の持続可能性につながることを強調しました。
日が暮れた後、参加者はホタルマップを片手に、鞍月用水沿いや庭園の池などを歩きながらホタルを観察しました。用水のそばや民家の庭でもホタルの光が確認され、市街地にも自然の営みが息づいていることに気づかされました。参加者は観察ポイントごとに確認できたホタルの数を調査シートに記録し、提出しました。
なお、今年は昨年に比べて確認されたホタルの数が少なく、気候や環境条件の影響が考えられます。今後も継続的な観察と記録を通じて、都市における自然環境の変化を見つめていくことが求められます。
こうした活動を通じて、都市における生物多様性への理解を深め、市民とともに自然と共生する地域づくりを目指していきます。
次世代リーダー育成プログラム 第1回講義を開催
SDGs、気候変動、生物多様性 ―世界と地域をつなぐ基礎知識を学ぶ
2025年6月25日、「石川金沢から世界を変える、次世代のリーダー育成プログラム 2025 研修コース」の第1回講義が金沢未来のまち創造館で開催されました。石川県内の高校から選ばれた15名の生徒が参加し、SDGs、気候変動、生物多様性などの地球規模課題について、国際的・地域的な視点から学ぶ機会となりました。
講義の前半では、国連大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS)の竹本明生プログラムヘッドが登壇し、「気候変動政策とSDGs:世界の現状と課題はどうなっているのか」と題して講義を行いました。竹本氏は、パリ協定やSDGsの枠組み、国際条約と国内政策の関係を整理しながら、再生可能エネルギー導入に伴う社会的・環境的リスク、日本のエネルギー・食料自給率の課題などを紹介しました。また、少子高齢化が進む中で、ユース世代の社会参加が持続可能な未来づくりに不可欠であることを強調しました。
後半では、UNU-IAS OUIKのファン・パストール・イヴァールス研究員が、「自然を活用した解決策による生物多様性と気候変動への対応 ― 金沢モデル ―」と題して英語で講義を行いました。気候変動と生物多様性の密接な関係(biodiversity-climate nexus)を起点に、金沢における自然共生型の都市づくりの実践事例を紹介しました。伝統庭園や神社林などの自然資源を活かしたグリーンインフラ、空き地の再活用、地域住民との協働による環境保全などの取り組みを通して、Nature-based Solutions(自然を活用した解決策)やJust Urban Transition(公正な都市の移行)、Climate Justice(気候正義)といった国際的な概念を地域の現場に落とし込むアプローチを紹介しました。
特に、「何が“公正”なのか?」という問いかけは参加者の関心を集めました。気候変動が環境問題にとどまらず、人口、ジェンダー、貧困、国際政治といった社会的要素が複雑に絡み合う課題であることへの理解が深まりました。
次回の講義は7月9日に開催される予定で、能登半島地震や豪雨災害の事例をもとに、地域課題とレジリエンスについて考えます。
都市生態系再生国際シンポジウム開催記念:現地エクスカーション
2025年5月21日、国連大学サステイナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(UNU-IAS OUIK)主催による「都市生態系再生国際シンポジウム」の一環として、金沢市内の自然・文化資源を巡る現地エクスカーションが開催されました。
国内外から参加した都市代表や専門家ら約20名が、金沢の水辺環境や文化的・歴史的景観、保全・再生活動などを視察し、都市の自然と文化が共生する取り組みについて理解を深めました。
金沢の水辺文化に触れる
午前中は、犀川沿いのウォーキングからスタート。都市中心部を流れるこの川は、市民に親しまれる憩いの場であり、100年の歴史を持つ犀川大橋も訪問しました。続いて、都市用水として整備されてきた鞍月用水と、その再生プロジェクトによって生まれ変わった「せせらぎ通り」を視察。かつて蓋掛けされていた用水を、市民と行政の協働で開渠化し、まちなかの自然景観として再生した取り組みが紹介されました。
歴史的庭園と都市生物多様性
千田家庭園では茶会を通じて、金沢に伝わる武家の文化と都市自然との共生を体感。さらに、西氏庭園では、用水を取り入れた庭園構造や、文化財としての価値、官民連携による保全の取り組みについて学びました。金沢市の「歴史的庭園振興プラン」も紹介され、市民や観光客が保全に関わる新たな仕組みづくりへの期待が高まりました。
観光と持続可能性のバランス
午後は、観光地として人気の東茶屋街を訪問。増加する観光客と地域の文化資源の保全との両立を目指した取り組みが紹介されました。続いて訪れた心蓮社では、禅と都市自然、人口減少社会における都市自然の役割について学び、このような場が持続可能なまちづくりの担い手となる可能性にも言及がありました。
参加者の声
参加者からは、「都市の中心に水の流れを利用した豊かな文化が栄えており、それらが共存していることに驚いた」「市民の参加が都市の再生を支えている点が非常に参考になった」など、多くの前向きな感想が寄せられました。
本エクスカーションは、都市の自然再生において文化や市民参加が果たす役割を体感的に学ぶ機会となり、翌日に開催予定のシンポジウムへ向けて大きな学びとなりました。
【開催報告】西家庭園にて文化的および生物多様性の価値に関する講演を開催
金沢市内には、建造物や用水、庭園や鎮守の森など、まちの歴史を今に伝える歴史遺産が数多く残されています。 金沢市では、それらの貴重でかけがえのない歴史遺産を次代へと継承すべく、調査や整備、活用など、様々な取り組みを行っています。
これらの取り組みの一環として、金沢市は9月28日から11月30日まで「金沢歴史遺産探求月間」を開催しており、国連大学サステナビリティ高等研究所(OUIK)もこのに協力しています。
この期間中、市の歴史的遺産を体験するためのイベントが複数開催されています。その一つとして、10月12日に国の名勝に指定されるために手続きが進められている西家庭園にて本イベントが開催されました。本イベントでは市の文化財保護課の招聘により、OUIKの研究者であるフアン博士が43名の参加者に向けて講演と庭園ツアーを行いました。

当イベントに金沢市長の村山卓も出席し、金沢の庭園文化の重要性と、国際的な認知の高まりについて語りました。村山市長は金沢の文化と環境が国連環境計画(UNEP)の「世代間環境回復プロジェクト」のモデル都市として世界的に認識されていることを強調し、金沢の環境、経済、文化の価値を促進する上でOUIKが果たす重要な役割に感謝の意を表されました。
講演の中でフアン博士は、金沢市を取り囲む自然の主要な特徴、特に山々や豊かな水資源について説明しました。そして彼は16世紀に前田藩によって築かれた支援的な社会構造と、北陸地方の気候が形作った金沢の庭園の独自性を強調しました。このシステムにより多くの職人からなる中産階級が栄えました。さらに職人たちの多くは地域の用水路を利用し、自宅の庭に水を引き、小さな兼六園を再現しようとしました。
続いてフアン博士は現在でも市内に残る用水や庭園の関連性について詳述しました。彼は、これらの庭園が人口減少や維持管理の不足に直面している課題を説明しました。講演の後半では、用水と庭園のつながりが市内の生態系機能、特に生物多様性の維持にとって不可欠であることを強調しました。
この点を証明するために、フアン博士は都市内の30か所の庭園で実施された野生動物調査(2021年9月、11月)の結果を紹介し、西家庭園を具体例として挙げました。
この調査では、現場観察、センサー付きカメラ、ICレコーダー、DNA分析などさまざまな手法を用い、季節ごとにデータを収集しました。その結果、アユやハヤブサ、ナミコキセル、ホタルなどの貴重な種が特定されました。これらの結果は、文化的保護と自然保護が強く結びついていることを示しています。多くの生き物が急速な都市化から守られている環境を求め、庭園に生息するようになりました。そのため現在、庭園はこれらの生き物の貴重な生息地としての役割を果たしています。
フアン博士の講演を通じて、参加者たちは金沢庭園の美的、文化的、そして生態学的価値について深い理解を得ました。ディスカッションセッションでは、生態系の継続性を確保するために、今後数年間、生き物の生態を追跡するモニタリングシステムを確立することが重要であると議論されました。その後、参加者たちは晴れた初秋の日に庭園を自由に散策し、楽しむことができました。
———————————————————————
*西家庭園について:西家庭園は、1916年(大正5年)に旧市街の長町の住宅地に作られ、その原貌を保ってきました。隣接する大野庄用水路は中央の庭池を潤し、その池は日本各地からの印象的で大きな景観石で囲まれており、アーチ型の橋や水の盆と美しく調和しています。また、庭の珍しい部分に配置された高い人工の丘は、松やツツジ、カエデなどの在来植物で植生されており、見る人に金沢の自然の特性を反映した深い空間感覚と隔絶した雰囲気を提供しています。
金沢市公式YouTubeチャンネルでイベントの概要をご覧ください。
【開催報告】石川金沢から世界を変える、次世代のリーダー育成プログラム 2024成果発表会
国連大学OUIKが今年度から新たに立ち上げた「石川金沢から世界を変える、次世代のリーダー育成プログラム」発表会が2024年9月16日に開催されました。本プログラムは、持続可能な開発や気候変動といった地球規模の課題に対し、地域からグローバルリーダーを育成することを目的としています。金沢市内の高校生13名が参加し、半年にわたって地域環境や気候変動に関する学習を進めてきた成果を発表しました。
発表会の内容:
発表会では、プログラムに参加した13名の高校生が、夏休みを利用して取り組んだ地域環境課題の探究プロジェクトの成果を発表しました。各学生は、気候変動の影響や地域の具体的な環境問題に対して、彼ら自身が考えた解決策や提案をプレゼンテーション形式で発表し、会場からの質問にも積極的に応じました。
発表されたテーマは以下の通りです:
- 耕作放棄地の活用
- 車社会からの脱却
- より良い港と周辺環境づくりに向けた提案
- 代替フロンの排出量削減について
- いしかわ・かなざわのまちと水
- 金沢におけるグリーンインフラについて
- サーキュラーエコノミー
学生たちの発表は、具体的なデータに基づいたものであり、現実的な解決策を提案する内容が多く見受けられました。特に、地域住民との連携や行政との協力を視野に入れた提案が、参加者の注目を集めました。
次のステップ:COP29への派遣
発表会終了後、参加学生たちは個別面接を行い、金沢泉丘高校の梶夏菜子さんと金沢大学附属高校の本多真理さんが選抜されました。この2名は、今年11月にアゼルバイジャンで開催される国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)に国連大学代表団、そして金沢のユース代表として参加することが決定しました。彼女たちは国際的な場で金沢の若者として積極的に意見を発信し、世界の気候変動対策に貢献することが期待されています。
今回の発表会は、地域の若者がグローバルな課題に対してどのように向き合い、自分たちの視点で解決策を提案するかを示す非常に意義深い機会となりました。学生たちの情熱と行動力に触れた参加者たちは、彼らが地域社会だけでなく、世界の未来を担うリーダーとして成長していく姿に大きな期待を寄せました。
COP29への派遣メンバーの活動報告は、国連大学OUIKの公式ウェブサイトやSNSを通じて順次発信される予定です。ぜひご期待ください。
菊川地区で参加型アクションリサーチ (Participatory Action Research: PAR)を開始
2024年5月14日
OUIKのフアン研究員はSustainable Urban Nature Project(持続可能な都市自然プロジェクト)の一環として参加型アクションリサーチ (participatory action research: PAR)を金沢市、菊川地区で開始しました。この地域において今年度、市民の参加を重視し、環境保護を促進し、放置されたスペースを活性化させることに焦点を当てた包括的な研究が行われます。
この参加型アクションリサーチ(PAR)活動には、共同問題解決、意識の向上、市民が経済的および環境的変化に効果的に適応するためのエンパワーも含まれます。
菊川でのPARイニシアティブは、次の5つの主要な行動を通じて自然豊かなコミュニティを育成することを目指しています:
- 緑(都市自然)の成長の促進
- 生物多様性のモニタリング
- 緑地の維持
- コミュニティガーデンの共同創造
- エコツーリズムの奨励
PAR活動のキックオフとして、最初のセッション「植物の植え付けを通じた緑の成長」が5月14日に行われました。女性が主体の15人の参加者がについて議論しました。
フアン研究員は、菊川地区でのPARの紹介と、近隣の緑化の利点と課題について発表しました。その後、地元の庭師の指導のもと、参加者は土地の準備、植物の植え付け技術、およびメンテナンスについての洞察を共有しながら、実際の植え付け活動に参加しました。
植え付けセッションの後、フアン研究員は参加者の自然の利点への認識、自然豊かなコミュニティーの輪を拡大する上での課題、および活動を通じて強化されたコミュニティの結束の指標を評価するための討論と調査を行いました。
次のPARセッションは6月28日に予定されています。このセッションでは、生物多様性のモニタリングが中心となり、市民科学者が菊川内の倉月水運河沿いおよび指定された2つの庭園でホタルの調査を行います。
このプロジェクトは、菊川地区でのポジティブな変化を推進し続けており、コミュニティの参加と持続可能な慣行を活用して、より自然豊かでレジリエンとな都市景観を創造しています。