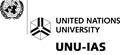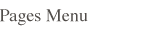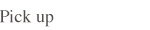2025年8月10〜13日、第41回国連大学グローバル・セミナー「気候危機とともに生きる:能登、金沢、白山から学ぶレジリエンスと持続可能な社会づくり」が石川県金沢市と白山市にて開催され、30名が参加しました。開会式では国連大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS)・所長の山口しのぶが開会の言葉を述べました。

1日目は3講義と能登からスペシャルゲストをお迎えしお話頂きました。
国連大学サステイナビリティ高等研究所 いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(UNU-IAS OUIK)渡辺綱男 客員研究員から「国際枠組みと生態系保護の課題」 について講義があり、保全努力だけでなく、生態系を積極的に回復・再生させていくアプローチが重要であると強調しました。
続いて、UNU-IAS OUIK小山明子 研究員から「能登の里山里海、2024年の地震と豪雨被害のその後」 について講義があり、能登の人々は代々、豊かな里山里海を利用しながら生活をし、人の手が加わることで生物多様性が維持され、自然と共生してきたことを説明しました。地震以前からの課題である過疎化も取り上げ、持続可能な地域づくりのための生態系を活用した防災・減災が必要であると述べました。
UNU-IAS ナフィサ・インセバエバ 研究員が「気候正義について」というテーマで講義を行いました。気候正義とは何か、誰が計画をし、誰が利益を得ているか説明しました。子ども、女の子や女性が最も気候変動の影響を受けており、なぜこれらの問題解決が重要なのか、どうすれば自分は行動変容ができるか、今回の講義を超えて考えてほしいと参加者に投げかけました。
1日目の最後に能登からのスペシャルゲスト、神谷健司さんから「奥能登の塩田村」についての講義でした。奈良時代に始まったとされる揚げ浜式の歴史や、塩田が作り出す自然との好循環について説明しました。地震や豪雨被害だけでなく、気候変動が塩づくりにも影響がある中、情報発信、他業者との協力をしながら、伝統的な塩づくりを続けていきたいと話しました。
2日目は金沢市で講義、兼六園見学のあと、白山市に移動し2講義が行われました。
UNU-IAS OUIKフアン・パストール・イバルス研究員から「金沢における持続的な都市自然と生物多様性」 について講義があり、金沢は地域の伝統的知識と住民の協働による自然との共生が長く続けられてきたことを紹介しました。また、庭園システムが都市内生態系の保全につながっていると述べました。
フアン研究員の講義の後、兼六園を訪れ、時雨亭で伝統的な日本茶道体験をしました。フアン研究員の説明を聞きながら庭を回り、金沢独特の庭園文化や庭園が生物多様性に果たす重要な役割について学びました。

奈良教育大学 及川幸彦准教授は「災害リスク軽減と気候変動、及びESD」について講義し、世界中で災害は発生しており気候変動によりその規模が拡大し、早期警報システムが周知されていなかったことが被害を悪化させていたことを説明しました。年々、気温や海水温度は上昇し、資源や生物多様性にも影響している中、防災・減災教育は世界中で取り組むべきものだと強調しました。
続いて、NPO白山しらみね自然学校 山口隆 さんより「白峰の生活様式の紹介」について の講義でした。白峰の暮らし、焼畑、ぜんまい干し、雪下ろし、報恩講料理、放楽相撲、民謡といった自然の力を利用し生活してきた固有文化について紹介しました。過疎化という課題がある中、豊かな資源や観光の力を利用しながら、白峰ならではの文化や暮らしを継いで、次世代の担い手が暮らせるまちづくりをしていきたいと述べました。
3日目は2講義のあと、テーマごとにわかれ、グループディスカッションをしました。
ユネスコ白山手取川ジオパーク促進委員会 スーザン・メイ 国際連携専門員から「白山手取川ジオパーク生物圏保護地区の特徴と活動」について講義があり、高山で豪雪地域である白山手取川ジオパークは、豊かな水源や多様な高山植物が、生物多様性をもたらし、人々は山の恵みを活かし、適応した生活が営まれてきたことが説明されました。教育、地域間のネットワークの強化や観光を通して、伝統文化の継承と発信を続けていきたいと述べました。
続いて、UNU-IAS勝間靖 アカデミックプログラムアドバイザーより「気候変動と健康」についての講義でした。若年層における気候変動への不安は、高い傾向があり、メンタルヘルスとウェルビーイングに悪影響を及ぼす可能性があると述べました。適応措置において、より踏み込んだ言及が必要で、災害軽減研究と緊急支援研究との多分野連携が不可欠であると強調しました。
午後は5つのグループに分かれ、生態系保全、教育、持続可能な観光、災害復興、気候と健康について議論・探求し、発表を行いました。


4日目の最終日は、白山国立公園を散策し、「百万貫の岩」から自然の力の大きさと水害の歴史を学び、わさび田では自然の恵みや、里山の活用方法について学びました。
今回の第41回国連大学グローバル・セミナーは、気候変動について知識を深め、能登、金沢、白山がどのように自然と共生してきたかを学ぶ貴重な機会になりました。講師への質問だけでなく、講義時間外でも、様々なバックグラウンドを持つ参加者同士で、それぞれの課題、地域レベルでの取り組みや世界とのつながりについて、意見交換が活発に行われたことが印象的でした。