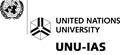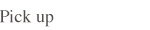OUIKでは、『地図情報から見た能登の里山里海』、『地図情報から見た金沢の自然と文化』をはじめ、地域の自然と文化のつながりを分かりやすく理解するための地図情報整備を進めています。
北陸地方を対象として、県レベル、市町村レベルでのマルチスケールでの地図情報を集約しています。その際に、生物多様性、文化多様性、生態系サービスといったキーワードを軸に、地域のニーズを反映しながら、視覚化や定量化に工夫し、地域に役立つ学びと情報発信のツールづくりを行っています。
地域との研究活動:アーカイブ
地図情報の集約:生物文化多様性や生態系サービスを理解する学びに貢献
ごっつぉ草紙 Red data cook book
2018年、国連大学OUIKでは「世界農業遺産(GIAHS)能登の里山里海」の価値を次世代に伝えるため、教育絵本「ごっつぉをつくろう」を制作しました。この本は季節ごとに様々な地域の食材を使いながら能登の祭りごっつぉ(ご馳走)を作っていく物語です。「食」を通じて能登の農業や生き物、文化の理解を深めることを目的としています。
2019年、このその絵本を元に輪島市で「地域に根ざした学びの場・まるやま組」では地域のご馳走の食材をあつめながら自然や文化について学ぶモデル授業「三井のごっつぉproject」を輪島市立三井小学校の児童を対象に行いました。
この「ごっつぉ草紙 Red data cook book」は一年を通して行ったこの教育活動の記録です。さらに授業の中では紹介できなかった地域に残る郷土料理や食材など「ふるさとの味」を季節ごとに紹介しています。
発行 2020年10月16日 World Food Day
制作 能登地域GIAHS推進協議会
協力 輪島市立三井小学校、輪島市三井公民館、市ノ坂集落、輪島エコ自然農、能登SDGsラボ、能登里山里海SDGsマイスタープログラム
企画・編集・デザイン・写真 萩のゆき(萩野アトリエ、まるやま組)
萩野紀一郎(富山大学芸術文化学部、まるやま組)
モニタリング・解説 伊藤浩二(岐阜大学、能登SDGsラボ連携研究員、まるやま組)
発行 国連大学サスティナビリティ高等研究所 いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(UNU-IAS OUIK)
能登生物多様性研究会の発足
能登の里山里海がFAOにより世界農業遺産(GIAHS)に認定されてから5年の節目を迎えようとしています。OUIKではそれに伴うアクションプランの改定作業やモニタリング作業の支援などを行ってきました。
中でも、4市5町にわたる能登地域で行われている生物多様性モニタリングの活動は、各市町や各種民間団体が独自に行っている生き物調査が中心であり、能登地域全体として統一されたモニタリング手法や生物多様性に関する情報発信や地域の方々と共有するしくみはまだ開発されていません。この現状を受けて、OUIKと金沢大学里山里海プロジェクトが中心となり、能登の生物多様性モニタリングや関連活動を通じて能登GIAHSに貢献するための生物多様性研究会を設立しました。メンバーには地域で生物多様性保全や環境教育に取り組んでいる民間団体の方々、能登の関連する研究機関の方々に参加いただいています。
1月23日には、OUIKがオブザーバーとして参加している、能登GIAHS活用実行委員会と能登GIAHS推進協議会の場で同会の発足を報告しました。今後は推進協議会の生き物しらべや関連する事業と連携しつつ、能登GIAHSとして豊かな生物多様性の保全とモニタリング、そして発信に貢献してゆきます。
白山ユネスコエコパーク協議会の参与メンバーとなりました

協議会で挨拶する渡辺OUIK所長
白山麓はユネスコエコパークとして(英語名:UNESCO Man and the Biosphere progaramme / Biosphere Reserve)1980年にユネスコにより認定されています。白山市は、白山手取川ジオパーク推進協議会事務局とユネスコエコパーク事務局を兼務しており、これは世界的にも珍しいケースとのことです。2016年白山エコパークにおいて移行地域の拡張申請を行うにあたり、白山地域を構成する4県7市村の自治体が中心となって2014年1月に協議会が発足しました。OUIKは2015年8月から協議会の参与として正式に就任し、エコパーク認定地域の計画見直しや承認プロセスについての情報収集や啓発普及のお手伝いをさせて頂くことになりました。

山田白山市長(左)から白山の自然と文化について伺いました。
2015年5月12日の第3回協議会の開催にあわせて、協議会会長である山田白山市長に、渡辺OUIK所長より参与メンバー就任のご挨拶をさせていただきました。ご自身も白山麓の出身である市長からは、白山の自然と文化について貴重なお話をたくさん伺うことができました。これからも地域が自然と共生するエコパークの理念を守りつつ白山麓の地域創生のお手伝いが出来ればと思います。
OUIK 生物文化多様性シリーズ#5 金沢の庭園がつなぐ人と自然 ー持続可能なコモンズへの挑戦ー
金沢の日本庭園の活用方法を防災、観光、景観など多面的なアプローチから解説すると共に、持続可能な都市と生態系保全に向けたアイデアを提唱しています。
アジア生物文化多様性国際会議開催一周年記念国際フォーラムシリーズ議事録〔電子版〕
2016年10月、石川県七尾市で開催された第1回アジア生物文化多様性国際会議から1年後、石川宣言の実施を推進するため、2回シリーズの国際フォーラムをが開催されました。
シリーズ第一回(2017年10月4日)
生物文化多様性とSATOYAMA -自然共生社会を目指す世界各国の取り組みを知る-
シリーズ第二回(2017年10月15日)
生物文化多様性を次世代が敬称する為に-東アジアの連携を考える-
国連持続可能な開発目標に向けた 青年キャパシティ・ビルデン グ・ワークショップ
日時 / Date : 2016/07/15 13:00 -17:00
場所 / Place : 金沢大学中央図書館 オープンスタディオ 2階
国連大学サステイナビリティ高等研究所と金沢大学留学生センターは、日本で学ぶ留学生によるSDGsワークショップを開催します。このワークショップは、7月11日から14日まで行われる、金沢市を中心としたSDGs達成のためのフィールドワークの報告会を兼ねています。金沢大学留学生センターに在籍する留学生、国連大学サステイナビリティ高等研究所のアカデミックプログラムの修士、博士課程で学ぶ留学生が「創造都市・金沢」を建築、エネルギー、教育、自然資源管理などの側面から議論します。
SDGsに興味がある皆様のご参加をおまちしております。言語は英語のみとなります。 ご登録は ryukou@adm.kanazawa-u.ac.jp まで氏名、御所属を記載のうえお送りください。
OUIK 生物文化多様性シリーズ#4 「地図から学ぶ北陸の里山里海のみかた」
OUIK初のマップブックとして、北陸地方の里山里海の現状や変化、多様な見方を地図から学ぶ教材を発刊しました。北陸地方(石川、福井、富山、新潟、岐阜)のスケール、石川県のスケール、七尾湾のスケールといったマルチスケールでの地図情報をまとめています。(PDF:95MB)
関連ページ(Collections at UNU) http://collections.unu.edu/view/UNU:6540
OUIK 生物文化多様性シリーズ#3「能登の里海ムーブメントー海と暮らす知恵を伝えていく」
2015年度からOUIKが能登GIAHSを構成する市町と開催してきた里海シリーズ講座の内容をまとめたものです。海を利用してきた地域に伝わる知恵、それらを守り、現在の社会環境に合わせて活用していく取組みをまとめています。
【開催報告】大阪・関西万博にて2日間に渡り、能登のプログラムを開催
2025年8月27日、大阪・関西万博プログラム「~CONNECTING YOU TO 能登~ 生物多様性(強く生き抜く生き物たち)について能登の小学生と学ぼう!」が、万博会場内のサステナドームにて、環境省と国連大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS)の連携で開催されました。
プログラム冒頭、国連大学サステイナビリティ高等研究所 いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット(UNU-IAS OUIK)小山明子 研究員は、生物多様性というコンセプトについて能登半島の生き物を例に紹介しました。参加者は生き物や環境、人の暮らしは全て繋がっていて、互いに支え合いながら成り立っているということを学びました。さらに、昨年発生した能登半島地震や豪雨を取り上げ、被害状況を述べました。
続いて、石川県能登町立柳田小学校5、6年生6名が、災害前から行ってきた町野川の水質調査や生き物調査の結果について発表をしました。災害後の生態系の変化、生き物の生命力の強さ、環境の変化が食物連鎖に与える影響について、彼らの考察を交えながら堂々と発表しました。
小学生による発表の後は、東京にいるさかなクンと会場をオンラインで繋ぎ、交流会を行いました。さかなクンが実際に能登を訪れた際に見た魚たちや、地震や豪雨、気候変動や環境に関する生き物たちが直面している課題について話しました。
最後に来場していた子どもたちからさかなクンへ質問が投げかけられ、さかなクンはその場で魚の絵を描きながら、好きな魚や魚の条件など詳しく説明し、こどもたちは興味深く聞き入っていました。
来場した子どもたちは能登の生き物や地震後の状況について学ぶ、貴重な機会になりました。
このプログラムを企画する上で能登里海教育研究所 そしてのと海洋ふれあいセンターにもご協力いただきました。

2日目の8月28日は「~CONNECTING YOU TO 能登~ 被災地に学ぶ防災と復興について能登の高校生と学ぼう!」は石川県立七尾高校の1、2年生5名が発表をしました。
冒頭の小山研究員による能登の里山里海の生業、伝統文化、暮らしに関する説明の後、生徒たちは、2024年の能登半島地震や豪雨での体験をもとに、地域での困難やそこで感じた思いを自らの言葉で語りました。また、震災・豪雨後の地域環境の変化に関する研究活動についても紹介し、「今目の前にある暮らしや環境は決して恒久に続くものではないことを実感したと」述べました。さらに、5ヶ月近く断水が続いた経験とともに水の大切さを語り、備えることで被害を少なくできるという考えも共有しました。災害から学び、それを未来へつなげる重要性を訴える姿は、参加者に強い印象を与えました。
発表の後にはワークショップが行われ、会場に集まった子どもから大人まで幅広い参加者が加わり、グループごとに意見交換を行いました。能登の高校生の発表を受けて、各自の地域での防災の在り方や日頃の備えについて話し合う時間となり、阪神大震災を経験した参加者が当時の体験を共有する場面もありました。こうした対話を通じて、世代や地域を超えた共感と学びが広がりました。
最後に、UNU-IASの山口しのぶ所長がプログラム全体を振り返りました。所長は「昨今の豪雨や森林火災といった災害は気候変動とも深く関わっており、能登や日本だけではなく、世界のどこでも起こり得る。だからこそ、世代や立場、地域を超えて多様な人々が学び合うことが、社会をより良いものにする力になる」と述べ、本プログラムの意義を改めて強調しました。


災害をテーマに据えながらも、能登の経験を起点に過去・現在・未来をつなげ、地域を超えて共に考える場となった今回のプログラムは、万博という国際的な舞台にふさわしい学びの機会となりました。