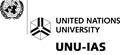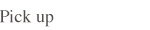2025年8月30日、石川県金沢市菊川にて、国連大学サステイナビリティ高等研究所 いしかわ・かなざわオペレーティングユニット(UNU-IAS OUIK)と特定非営利活動法人「綴る」 の共催で、畑トーク Vol.1 「能登と金沢をつなぐ緑の対話:里山の知恵と再生のかたち」を開催しました。学生、研究者、地域の方、専門家など約30名が集まり、2時間にわたり活発な意見交換を行いました。
オープニングトーク
はじめにUNU-IAS OUIKのフアン・パストール・イーヴァルス研究員より、金沢の都市自然の保護保全・再生のために進めている「持続可能な都市自然プロジェクトの参加型アクションリサーチ (Participatory Action Research: PAR)」について紹介がありました。
PARは①都市の緑地化②生物多様性観察③緑地の整備④共同⑤エコツーリズムを柱として市民と共に展開されてきました。フアン研究員は、今回の対話の場はこれからの取り組みをさらに発展させ、地域の考察を深め、都市と地位社会のつながりを強化する重要なステップになると強調しました。さらに、今年初めに能登を訪問した際、住民が「震災後に緑や美しさを取り戻したい」と語ったことに感銘を受けたと述べ、畑が金沢と能登をつなぎ、癒しと回復の象徴になり得ると語りました。
プレゼンテーション
続いて、特定非営利活動法人「綴る」の松本有未代表理事が不動産の専門家かつ地域活性化を推進する立場から発表しました。「綴る」が空き家を再生し、文化交流や食事の場、コミュニティ形成の場へと変えてきた事例を紹介し、イベント会場の「イクヤマ家」がその象徴的な成果であると話しました。
基調講演は、のがし研究所の萩のゆき氏が「まるやま組〜のがし研究所〜の庭、なつかしいのに、あたらしい、これからの能登」というテーマで発表しました。デザイナー、環境活動家、コラムニストとしての経験を交えながら、10年以上にわたり地元の方々から伝統的な里山の知恵を学んできた、能登での生活を語りました。2024年の能登半島地震については、家屋や生計手段が失われた一方で空き地に木や花を植えて憩いの場が作られたり、瓦礫を利用した創造的な再利用など、新しい実践が生まれたことを紹介しました。特に、瓦礫から作られた苔のプランターは参加者の関心を集め、里山の知恵が都市再生や集団的な癒しに貢献し得ることを示しました。


グループディスカッション
イベントの後半では参加者も交え、4つのグループに分かれ次の事を話し合いました。
- グリーンインフラ*の利点 – 優先すべきものとその理由
*社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する 多様な機能を活用 し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組
- 保全と転換 – 既存の緑地の保護か、空き地の再利用か
- 拡大とガバナンス – PARイニシアチブを他の地区へ拡大し、自治体の政策立案に組み込む
- レジリエンスとウェルビーイング – 里山の知恵を災害復興と都市生活に応用する
議論では、グリーンインフラは地域のアイデンティティやニーズに根ざす必要がある指摘され、保全を優先しつつも段階的な変革を組み合わせることが重要とされました。参加者は、PARを教育と結びつけることの意義、公共団体との連携強化、マルチステークホルダー・ガバナンスの促進についても強調しました。共有された里山の知恵は、信頼できる、回復力がある、人間が創造する都市の未来のための貴重な指針との意見もでました。
これからについて
イベントは菊川のコミュニティーガーデンでの農作業体験でで締めくくられました。参加者は、この交流が里山実践への理解を深めただけでなく、金沢と能登の地域コミュニティ間の絆を強めたと話しました。

UNU-IAS OUIKの観点から、今回の第1回「畑トーク」は、社会生態系の回復とウェルビーイングに関する共有ビジョンを生み出すための、都市と農村の対話の潜在的可能性を実証することができました。このイベントは今後数か月間継続され、能登から新たな声を届ける追加セッションを通じて、さらに議論を豊かにしていきます。