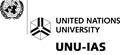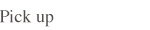2025年3月20日、金沢市文化ホールにて、能登半島地震と記録的豪雨で被災した能登地方の復興や防災を考える能登復興支援 国際シンポジウム『災害に強い地域の復興を目指して – 能登・東北・世界から学ぶ自然を活かした防災・減災』が開催されました。
山口しのぶ(UNU-IAS所長)と北村裕一(石川県企画振興部次長)による開会あいさつで始まりました。その後、基調講演で、柳井清治(石川県立大学特任教授)、ユセフ・ナセフ(UNFCCC(国連気候変動枠組条約)適応部門ディレクター)とエヴァ・クラウス(ドイツ連邦共和国美術展示館ディレクター)にご登壇いただきました。

石川県立大学の柳井清治特任教授
柳井清治(石川県立大学特任教授)は能登地域での地震・豪雨による被害の状況や里山・里海の変化について説明し、特に地盤の隆起や豪雨による生態系への影響を指摘しました。未来の課題としては、被害を受けた森林の再生、土砂の制御、生態系に配慮した河川環境の再生、隆起海岸の教育的活用が必要であると述べました。

UNFCCC適応部門のユセフ・ナセフディレクター
続いて、ユセフ・ナセフ(UNFCCC適応部門ディレクター)は「変わりゆく世界における自然・文化・生業:能登半島からの学び」をテーマに発表し、世界各地で大規模災害が続発するリスクが高まっているとし、「復興と復旧に対する考え方を見直す必要がある」と強調しました。能登で発災後や復興への取り組みの中でみられた地域の助け合い、などは重要な学びを与えてくれると述べました。

ドイツ連邦共和国美術展示館エヴァ・クラウスディレクター
エヴァ・クラウス(ドイツ連邦共和国美術展示館ディレクター)は、「ヨーロッパ建築のレジリエンスと復興」をテーマに発表し、創造的で持続可能なヨーロッパの建築の事例紹介を通じて気候変動への対策(備え)と建築材料を再利用することの重要性を強調しました。

パネルディスカッションの様子。左から渡辺綱男客員研究員、灰谷貴光氏、小山明子研究員、大野長一郎氏、トーマス・エルムクビスト教授及び齊藤修博士
後半のパネルディスカッションでは 渡辺綱男(UNU-IAS OUIK 客員研究員)がモデレーターを務めました。 パネリストには、灰谷貴光(能登町復興推進課)、小山明子(UNU-IAS OUIK研究員)、大野長一郎(株式会社ノトハハソ代表)、トーマス・エルムクビスト(ストックホルム大学ストックホルムレジリエンスセンター教授)と齊藤修(IGES (地球環境戦略研究機関)生物多様性と森林 戦略マネージメントオフィス上席研究員)が参加しました。「災害に強い地域の復興と防災」というテーマで、パネリストが各自の経験を基に意見を交わしました。
大野さんは震災後の事業継続の難しさについて、灰谷さんは地域の特性を活かした防災計画の重要性を指摘し、エルムクビスト教授は「回復的トポフィリア(特定の場所や環境に対する愛着)」の概念を通じて被災地で緑化などの環境回復活動に参加することが心理的なトラウマからの回復やコミュニティーの繋がりの構築に貢献することを強調しました。齊藤上席研究員は能登半島でよく見られる「おすそ分け文化」が災害時に地域を支える可能性について述べ、小山研究員は井戸水の重要性とコミュニティの支え合いについて触れました。
パネルディスカッションの終わりに、環境省とIGESからのコメントをいただきました。石川拓哉(環境省地域循環共生圏推進室 室長)は、能登地域の自然資源 — 井戸や簡易水道など — が地域のレジリエンス強化に直結していることを実感した一方、復興の過程においては依然として多くの課題が残っていることとも指摘しました。加えて、武内和彦(IGES理事長)は、災害後の復興を進める中で、生態系を生かした自然の再生と人々の暮らしを取り戻す取り組みが今後の課題となることを述べ、持続可能な未来の実現に向けて、地域の皆様と共に考え能登の復興に取り組むことが重要であると締めくくり、コメントを終了しました。
最後に、閉会時の挨拶でシャオメン・シェン(国連大学欧州事務所(UNU-VIE)副学長、国連大学環境・人間の安全保障研究所(UNU-EHS)所長)は、「適応」の漢字には広い心で変化に対して動いていくという意味が含まれていること、そして「希望」の漢字には新しい時代の到来をまちのぞむという意味があることを説明し、広い心で新しい章の始まりに希望を持ち続けることが長期的なレジリエンス(しなやかな適応力/回復力)の実現と復興に不可欠であると述べました。
本シンポジウムは、UNU-IAS、環境省、石川県、公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)、公益財団法人国連大学協力会(JFUNU)の共催のもと開催されました。また、応用生態工学会、日本造園学会、2030生物多様性枠組実現日本会議(J-GBF)、経団連自然保護協議会、環境再生保全機構、公益財団法人イオン環境財団、日本景観生態学会、環境研究総合推進費S21、北國新聞、北陸中日新聞にご後援いただきました。
詳細については以下の動画(シンポジウムの録画)をご視聴ください。
※関連記事
・自然災害からの復興とレジリエントなコミュニティの形成を議論 – Institute for the Advanced Study of Sustainability
・能登復興シンポジウムが複数のメディアに掲載 – Institute for the Advanced Study of Sustainability